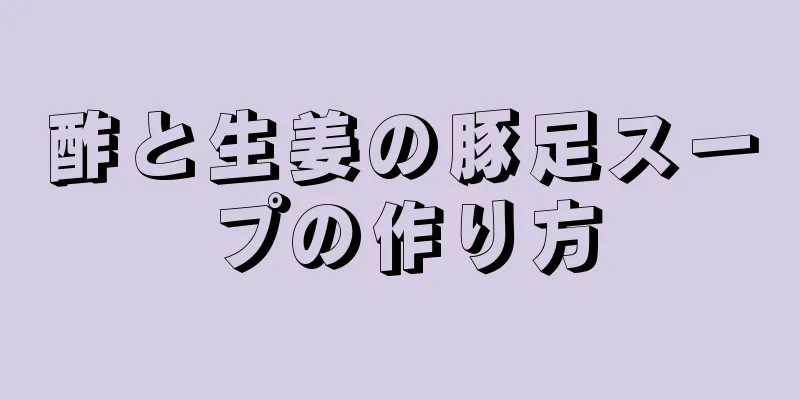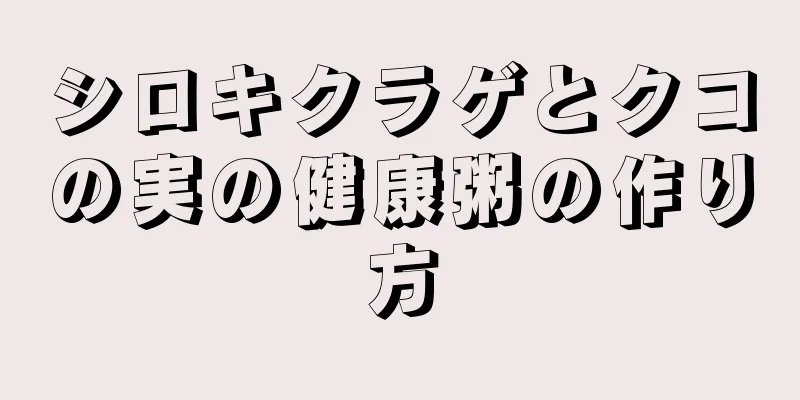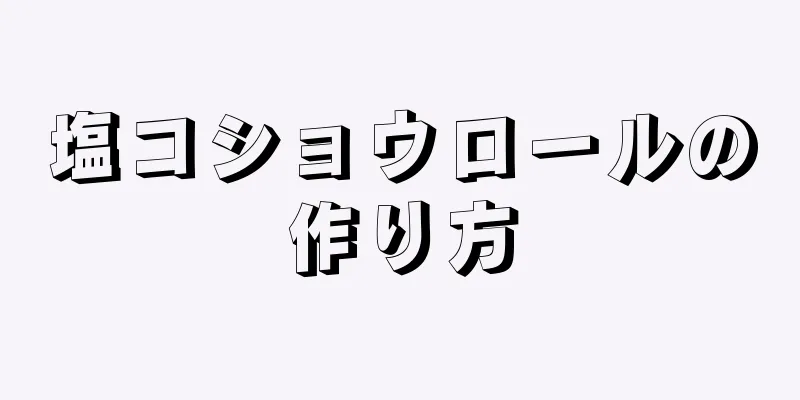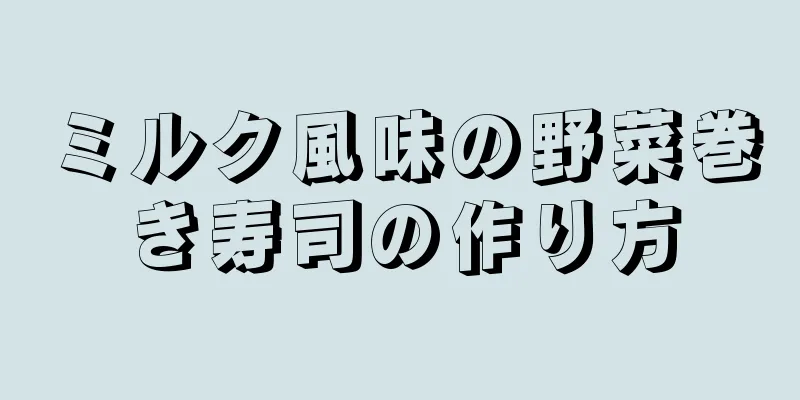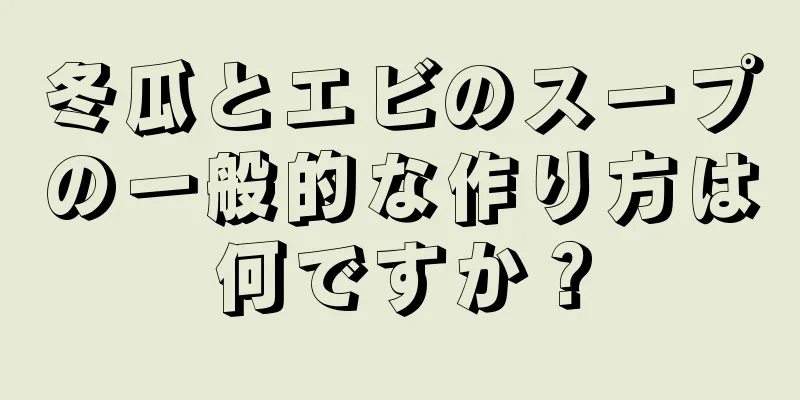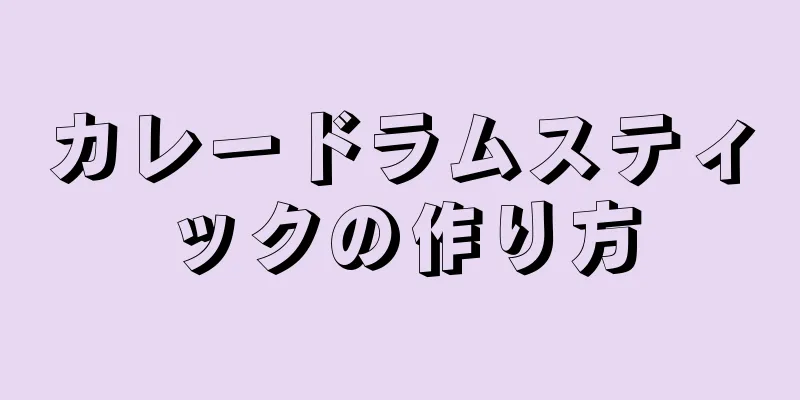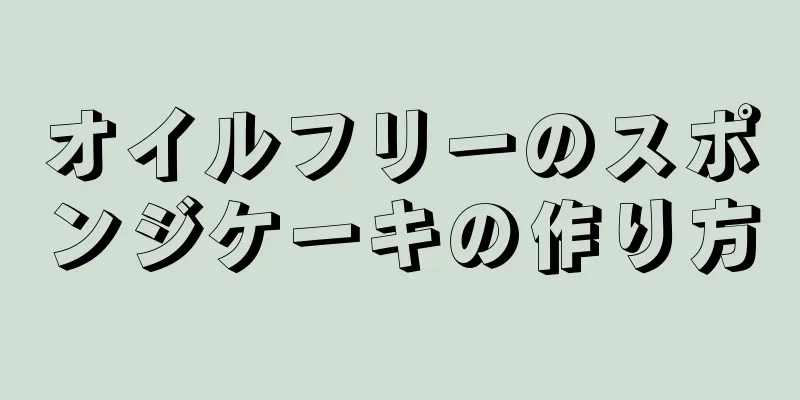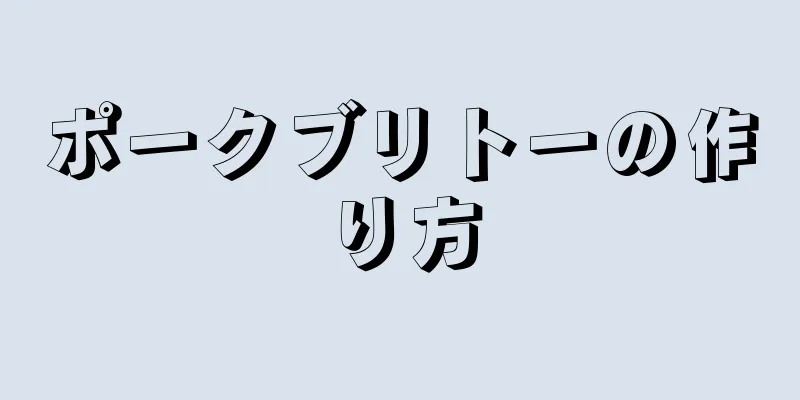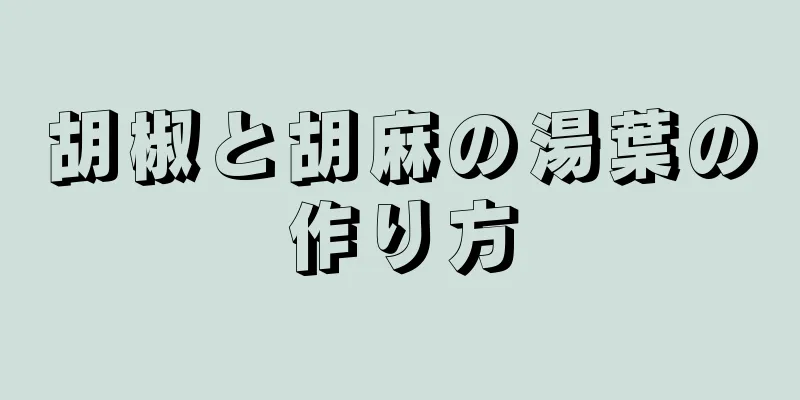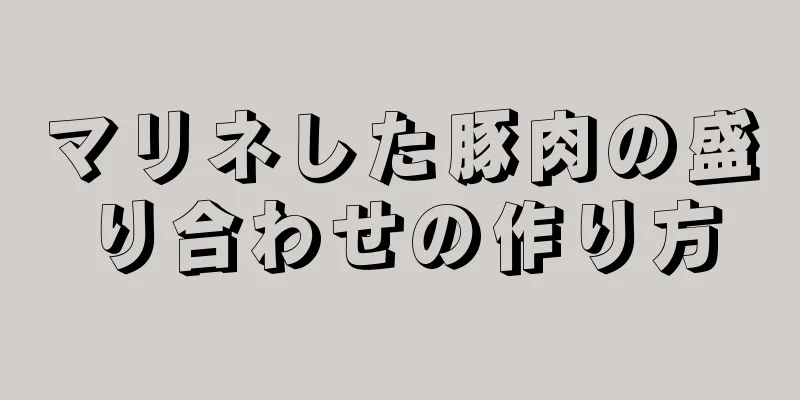小豆団子の作り方
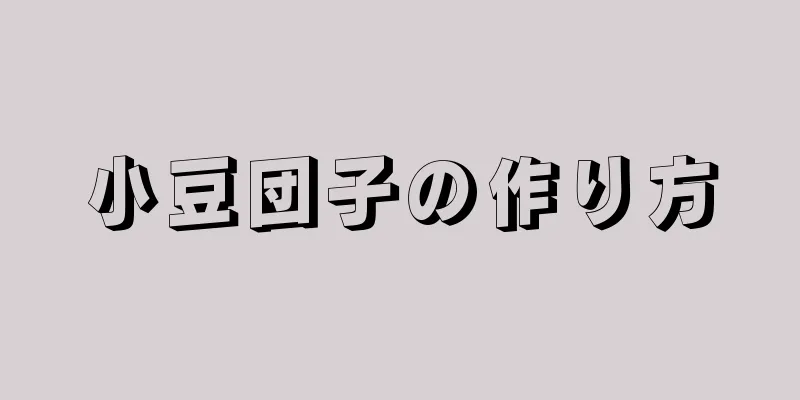
|
端午の節句には、多くの伝統的な行事や食べ物が受け継がれていきます。端午節は詩人屈原を記念する祭りです。端午節には、ドラゴンボートレースが行われ、団子作りが行われます。小豆団子、あん団子、肉団子など、団子の種類はどんどん増えています。ちまきにはさまざまな作り方があります。ここでは、小豆と米を使ったちまきの作り方についてお話しします。 小豆と米の団子のレシピ: 1. もち米を洗い、砕けるまできれいな水に浸し、置いておきます。 2. 小豆を洗い、1時間半浸した後、もち米と混ぜて置いておきます。 3. 団子の葉300グラムを洗い、鍋に入れて30分ほど煮て取り出し、冷水に浸して置いておきます。 4. 浸して洗った稲葉を3~4枚並べ、円錐形の筒状に丸め、混ぜ合わせたもち米と小豆を入れて団子状に包み、紐でしっかりと結びます。 5. 包んだ団子を鍋に入れ、水を加えて強火で約2時間煮込み、その後弱火で約3時間煮込んでからお召し上がりください。 食べてはいけないもの:小豆:鯉と小豆は一緒に調理すると利尿作用が促進され、腫れが軽減されます。腎炎による浮腫の治療に非常に効果的です。しかし、利尿作用が強すぎるため、普通の人は同時に食べることは避け、数時間間隔をあけて食べるようにしてください。一緒に食べられるかどうかは、人によって体質が異なります。 小豆団子を食べることの利点: 1. もち米の栄養:もち米は伝統的な季節の食べ物です。もち米は、その新鮮な香りが「豊作と幸運の年」を意味するほか、気を補い、胃を温めるなど穏やかな滋養効果もあるため、春に食べるのに適しています。もち米にはタンパク質、脂肪、炭水化物、カルシウム、リン、鉄、ビタミンB群、デンプンが含まれており、体を温めて強壮するのに適した食品であり、中を補って気を補い、脾臓と胃を温める効果があります。定期的に摂取することで、胃の虚弱や風邪による吐き気、食欲不振、神経衰弱、筋力低下、肉体疲労、妊娠中の腹部膨満などの症状も改善されます。 2.小豆の栄養:小豆は、小豆、小豆、小豆、小豆とも呼ばれ、高タンパク質、低脂肪、高炭水化物の食品です。ご飯やお粥と一緒に調理できるため、「米豆」とも呼ばれています。小豆はマメ科ササゲ属に属し、直立または蔓性の一年草で、マメ科植物のアズキの成熟した種子です。小豆は栄養価が高く、さまざまな食品に加工することができ、人々に愛され、良質な穀物と言えます。小豆は色が鮮やかでおいしく、薬用としても食用としても利用され、誰からも愛されている豆です。測定によると、小豆は栄養が豊富で、小豆100gあたりタンパク質20.0g、脂質0.5g、炭水化物58.5g、粗繊維4.9g、総食物繊維23.5g、微量のビタミンB1 0.3mg、B2 0.11mgなどが含まれています。また、カルシウム67.00 mg、リン305.00 mg、鉄5.20 mg、チアミン0.31 mg、リボフラビン0.11 mg、ナイアシン2.70 mgも含まれています。 |
推薦する
シュガーパンの作り方
健康的な食事を作るとはどういう意味ですか?少なくとも自分でやらないといけないようです。さて、ここでシ...
菊とエビの豆腐の作り方
現代生活の継続的な向上に伴い、人々の食生活に対する要求はますます高まっています。安全で栄養価の高い食...
もち米と白キクラゲの発酵スープの作り方
人生において、誰もが「食べること」という言葉なしには生きていけません。それは、私たちが生きていくため...
チーズピザの作り方
喧騒が終わった後に家に帰って美味しい食事を作るのは、とてもロマンチックで幸せなことです。たくさんの調...
牛肉マオカイの作り方は?
牛肉を使って茅菜の味を作るのは難しくありませんが、より多くの材料が必要です。時間に余裕のある友達は作...
チーズチョコレートムースケーキの作り方
人生において、親元を離れて一人暮らしをする人の多くは、料理の仕方が分からないかもしれません。私たちは...
蒸しピーコックブリームのレシピ
健康的な食事を作るとはどういう意味ですか?少なくとも自分でやらないといけないようです。さて、蒸し鯛の...
バナナ ストロベリー パパイヤ ミルクセーキのレシピ
自分へのご褒美として定期的に旅行しましょう。外に出て景色を眺めると、幸せな気分になり、健康にもなりま...
キノコチャーハンの作り方
ストレスがたまっている、食生活が不規則である、健康状態が良くないといった不満を訴える人は少なくありま...
エリンギとインゲンソースの麺の作り方
私たちが幼かった頃は、母親が近くにいたので、料理は簡単だと思っていました。私たちが成長して独り立ちす...
みかんの皮、白キクラゲ、梨のスープの作り方
現代人の多くは非常に忙しいため、定期的に自宅で料理をする人はほとんどいません。そして忙しさは彼らの大...
ミルクパンプキン、ミルク紫芋、ミルク小麦粉、ニンジン、フレッシュミートパンの作り方
会社員は仕事が忙しくて自分の健康管理ができないことが多いため、外食を選択することがありますが、時間が...
牛肉とキノコの鍋レシピ
多くの場合、私たちは仕事が終わった後においしい食事を楽しむことができるので、料理ができる親戚がいるこ...
ワイルドライスの茎とキノコを使った肉の炒め物の作り方
私たちの生活は友人から切り離すことはできず、友人同士の集まりは避けられません。一緒に食事をするのは幸...
ベイクドベビーポテトの作り方
人生には、学校に通い、働き、結婚し、子供を産むという過程があります。ほとんどの人にとって、すでに第2...