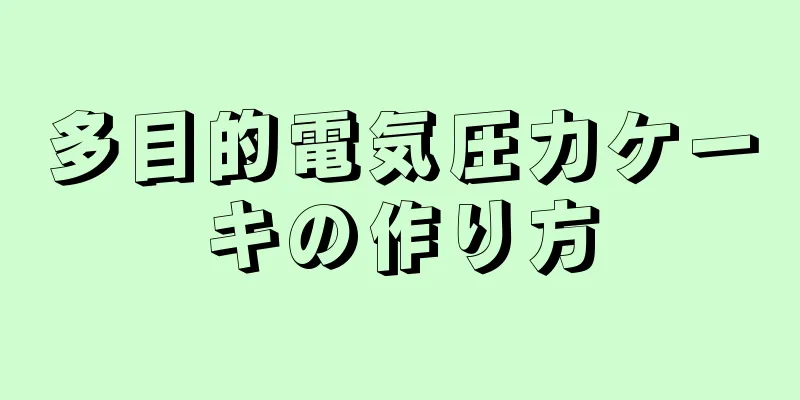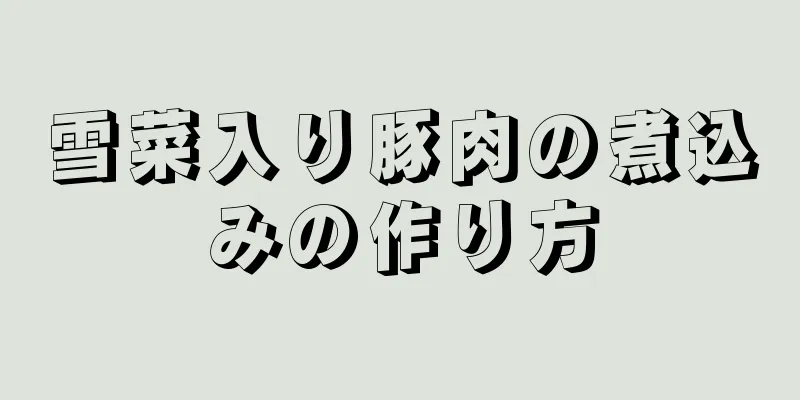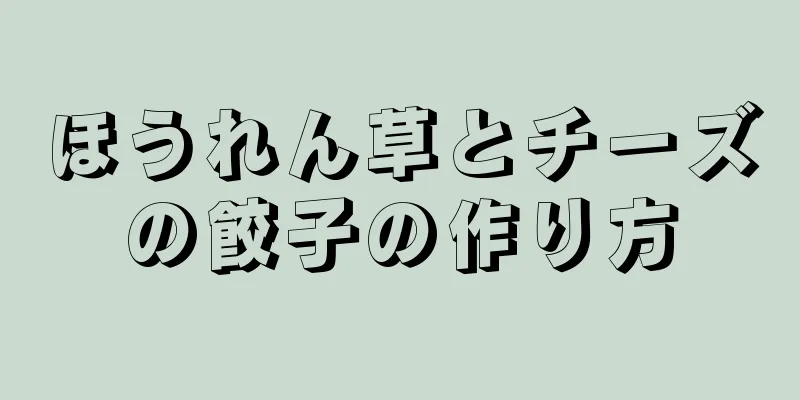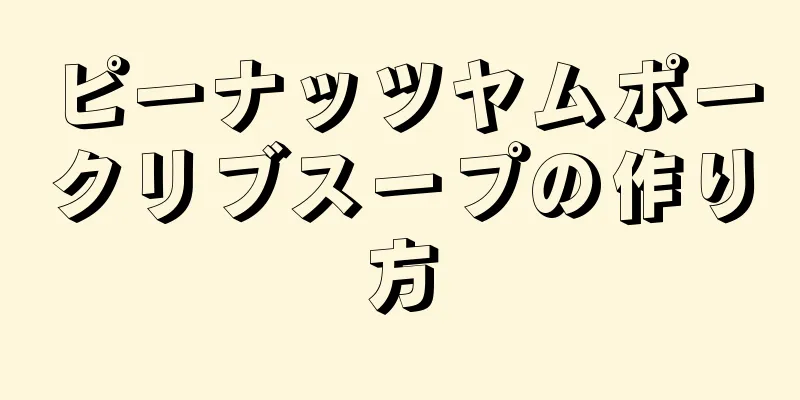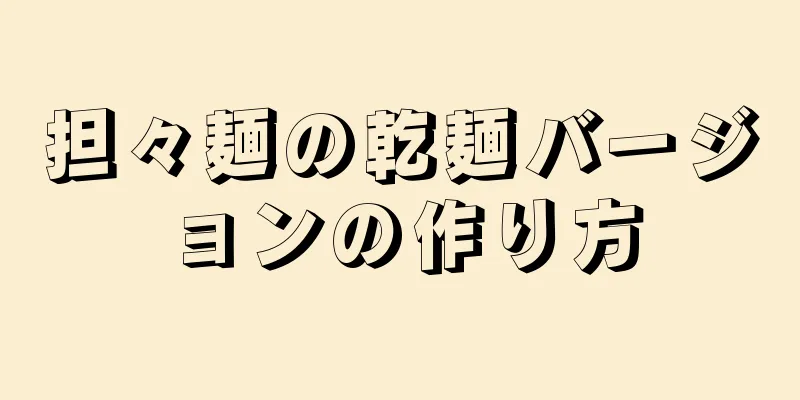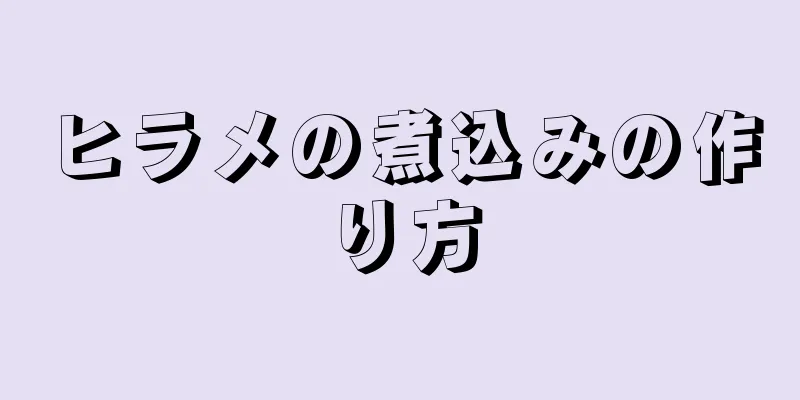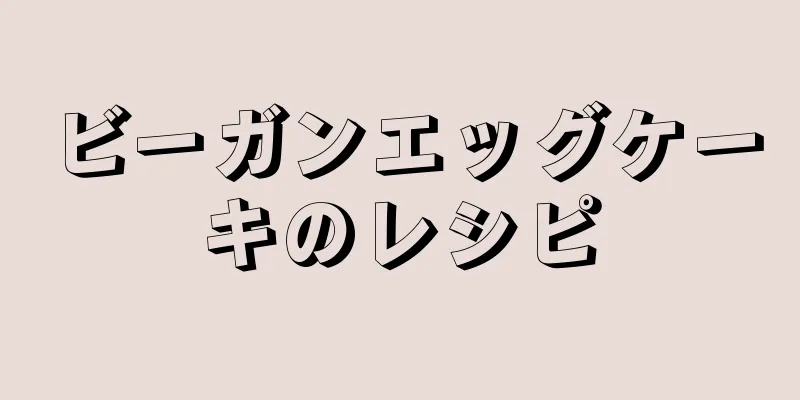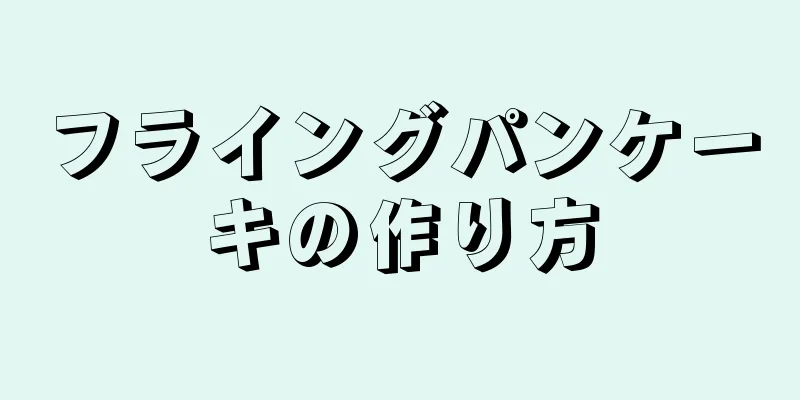オーストラリア産アワビの調理方法
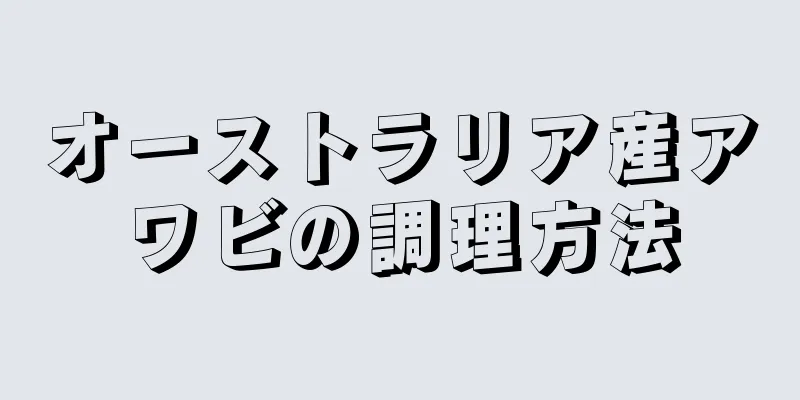
|
仕事や勉強で忙しい一日を過ごした後、空腹な体で夕食の準備をするのは本当に疲れます。オーストラリア産アワビのレシピはシンプルで覚えやすいです。必要なのは中華鍋だけです。揚げたり、揚げたり、煮込んだりする必要はありません。澄んだスープと一緒にお召し上がりいただくと、おいしい味をお楽しみいただけます。 1. 干しアワビを洗い、油や塩分を含まない容器に入れて、きれいな水に浸します。干しアワビがかぶるくらいの水を加えます。 2. オーストラリア産の干しアワビを浸す準備をします。 3. 水を頻繁に交換し、次のステップに進む前に 48 時間浸します。 4.鍋にアワビを入れ、純水を加えて強火で沸騰させ、その後中火にして30分煮ます。この時点でアワビがまだ固い場合は、さらに30分ほど調理してください。火を止めて鍋に蓋をし、6~8時間ほど放置します。調理したアワビを油や塩分を含まない弁当箱に入れ、精製水を加えて蓋をし、冷蔵庫の鮮度保持層に入れて浸し続けます。アワビが完全に浸って柔らかくなるまで。まだ浸っていない場合は、上記の手順を繰り返します。 5. アワビの口に切り込みを入れ、食道管を取り除きます。 6. 浸したアワビの膨張率は約2.5倍です。 7. 金華ハムを半分に切り、千切りにした生姜とネギを加え、魚臭さを取り除いて圧力鍋に入れ、強火で沸騰させ、中火にして15分間煮ます。 8. 材料を準備します。 9. 鶏の手羽を洗って湯がいて置いておきます。 10. 浸した黄金砂参を洗い(浸し方は、湯通しした黄金砂参のレシピを参照してください)、切り分けて置いておきます。 11. アワビをキャセロールに入れて30分ほど煮ます。 12. 金華ハムが調理されました。千切りにした生姜とネギを取り除きます。 13. すべての材料をキャセロールに入れて中火で3時間煮ます。より風味豊かにするために、長く調理することもできます。 14. 3時間後、醤油と少量の塩を加えてさらに10分ほど煮ます。 15. 火からおろす 16. アワビのクローズアップ写真 病気になったときに初めて、私たちは健康の大切さに気づきます。オーストラリア産のアワビは調理が簡単で、人々の健康維持に役立ちます。 |
推薦する
絞りたてのナツメジュースの作り方
結婚している方なら、間違いなく「奥様料理」の扱いを楽しめます。しかし、妻が家にいないときはどうすれば...
あんこサゴプリンの作り方
健康的な食事をしたいなら、自分で食事を作る必要があります。そうすることでのみ、健康でいられるのです。...
ジェイドシュリンプの作り方
美しく充実した子供時代は、必ずその人の人生に影響を与え、促進効果をもたらします。もちろん、子供時代の...
麗江ババの作り方
食べ物は人間にとって最も重要なものです。毎日健康的で栄養価の高い食べ物を食べることによってのみ、私た...
芋虫の作り方
腸内毛虫の準備は、誰もが考えるほど複雑ではありません。まずは食器と調味料を準備しましょう。次に、手順...
ポテトパンケーキの作り方
生きている限り、食べなければなりません。そして、長生きしたければ、もっと良いものを食わなければなりま...
抹茶ヌガーの作り方
多くの母親にとって、赤ちゃんや愛する人たちが健康的な食事を摂れば、病気になる頻度も減ります。今日は、...
カラフルな牛肉キューブの作り方
生活環境の悪化や勉強や仕事のプレッシャーの増大により、私たちの健康は徐々に蝕まれており、健康維持のた...
茄子とアサリの煮込みの作り方
日常生活において、ナスは誰もがよく知っている食べ物です。ナスは私たちの生活に欠かせない食べ物です。栄...
牛の胃袋を焼き過ぎずに揚げる方法
誰もが、煮過ぎてひどい味の料理を食べた経験があると思います。この味覚体験は非常に悪いです。牛のもつ煮...
仙居麦餅の作り方
仙居麦餅の作り方はとても簡単です。主な材料は生姜、果物、胡椒です。特にオフィスワーカーに適しており、...
スイカの皮と豚肉の餡を使った餃子の作り方
健康な体を維持するには食べ物が必要です。1日3食を不注意に扱って胃腸を悪くするのは残念です。普段から...
卵白ミルクトーストの作り方
卵白ミルクトーストの作り方は、みんなが思っているほど難しくありません。まずは必要なものを準備し、手順...
塩卵黄入り焼き芋の作り方
私たちの多くは料理の作り方を学びたいと思っていますが、どのように学んだらよいか分かりません。ここでは...
麺巣の作り方のレシピは何ですか?
武漢に行ったことがある人なら誰でも知っていると思いますが、面窩は武漢の昔から現代まで受け継がれてきた...